
春の訪れを告げる桜の淡いピンク色は、見ているだけで心が安らぎますよね。
日本を象徴する花として、多くの人に愛される桜ですが、その花言葉には「怖い意味」があるという噂を聞いたことはありませんか?
今回は、桜の花言葉に隠されたかもしれない影、そしてその真実に迫ってみたいと思います。
桜の花言葉
まず、一般的に知られている桜の花言葉から見ていきましょう。
「精神美」「優美な女性」「純潔」
「精神美」「優美な女性」「純潔」。
どれも桜の持つ清らかで美しいイメージにぴったりですよね。
満開の桜が織りなす景色は、まさに息をのむほどの美しさで、その姿は古くから多くの歌や物語に描かれてきました。
怖い意味がささやかれるようになった理由
では、なぜ「怖い意味」という言葉が囁かれるようになったのでしょうか?
調べてみると、直接的に「怖い」という意味を持つ花言葉は、少なくとも一般的なものとしては見当たりませんでした。
しかし、いくつかの要素が、そうしたイメージを生み出している可能性がありそうです。
フランス語の花言葉
例えば、桜の花言葉の一つに、フランス語で「私を忘れないで (Nem’oubliez pas)」というものがあります。
これは、一見するとロマンチックな言葉に聞こえますが、別れのシーンで贈られることもあるため、少し切なく、人によっては「怖い」と感じてしまうのかもしれません。
複数存在する別意味の花言葉
また、「ごまかし」や「淡泊」といった花言葉も存在します。
「ごまかし」は、桜の花が他の葉に先駆けて咲き、あたかも春が来たかのように見せる様子からきたと言われています。
少し意外な言葉ですが、特に怖いという印象はないかもしれませんね。
「淡泊」は、桜があっという間に散ってしまう、その潔すぎる様子から連想されたようです。
散り際の美しさも桜の魅力ですが、その儚さに寂しさを感じる人もいるかもしれません。
昔の日本でのネガティブイメージ
さらに、歴史を遡ると、江戸時代までは桜に対して少しネガティブなイメージを持っていた時代もあったようです。
散りゆく姿が「死」や「終わり」を連想させたり、花びらの色がすぐに変わってしまうことから「心変わり」を意味すると考えられていたという説もあります。
美しいものほど、その終わりは寂しく感じられるのかもしれませんね。
縁起が悪いという迷信
「桜を庭に植えると縁起が悪い」という迷信を聞いたことがある方もいるかもしれません。
これは、桜の成長が早く、根が広範囲に伸びるため、家を傾けてしまうといった実害から生まれた迷信のようです。
また、戦時中には、多くの人が亡くなった場所に桜が植えられたという背景から、少し物悲しいイメージを持つ方もいるかもしれません。
桜の花言葉に怖い意味はない
このように見ていくと、桜の花言葉そのものに直接的な「怖い意味」はないものの、その背景にある文化や歴史、そして儚さといった要素が、人によっては少しネガティブな印象を与えてしまうことがあるのかもしれません。

みつばんの個人的な解釈としては、桜の美しさはもちろんですが、その潔く散っていく姿に、力強さや潔さも感じます。終わりがあるからこそ、今この瞬間の美しさが際立つのではないでしょうか。少し切なくも感じますが、それは決して「怖い」という感情ではなく、過ぎゆく 時 の流れの中で、精一杯生きる桜の姿への 敬意 なのかもしれません。
まとめ
結局のところ、花言葉の解釈は人それぞれです。
桜を見て何を感じるか、どのような意味を見出すかは、その人の心次第なのかもしれませんね。
今年もまた美しい姿を見せてくれる桜に、感謝したいとおもいます。
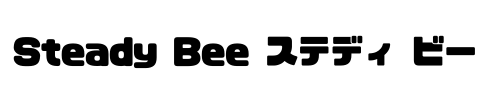



コメント