
秋も食中毒が増える時期。
この季節はお弁当を作る機会も多いですよね。
貴重なお米を大切に利用したい!
食中毒の可能性を最小限にするために保存方法に注意する必要があるんです!
この記事では食中毒を予防するための保存方法をお伝えします。
結論をいうと「食べきらない分をすぐ冷ます」「空気を遮断」「冷やして保存」です。
ご飯の保存方法
ご飯を炊き終わったあとどうしていますか?
炊飯器に入ったまま朝まで?食べきるまで数日放置?
土鍋で炊いて、おひつに移すという方もいるかもしれませんね。
炊いたご飯はすぐに冷ます
炊きたてのご飯は一部の病原菌にとっては理想的な繁殖環境です。特に室温で長時間放置することは危険です。早めに冷ましましょう。
食べる時間に炊きあがるように炊飯して、残りご飯はすべてすぐに冷まして保存用にすることが理想です。
実は「保温しながら炊飯ジャーの中に放置」はNGです。
冷蔵庫、冷凍庫で保存する
炊いたご飯を保存する時は、粗熱をとってから冷蔵庫で冷やしてください。
すぐに使わない場合は冷凍庫へいれてください。
 | 価格:3340円 |
温める時は十分に加熱する
再加熱する時は、ご飯がしっかりと加熱されるようにします。
76度以上に加熱することで殺菌効果を高めることができます。
保存容器は密閉できるものを
古かったり、傷がついていたり、熱で歪んでいたりする容器は使用しないでください。
密封できる容器を使用することで外部からの菌の侵入を防ぐことができます。
ご飯を1食分ずつ保存容器にいれるかラップに包んで保存すると、密閉度が高まります。
長期間の保存は避けて
炊いたご飯は原則として冷蔵庫なら2日間までの保存が望ましいです。意外と短いですね。
長時間保存する場合は冷凍しましょう。
ご飯の食中毒ってどんな菌が原因なの?
ご飯は炊くときに高温で加熱しますよね。
最初のお米と水の段階で熱に弱い菌は死滅します。
ご飯に菌が繁殖する原因は、加熱に強い菌だったケース。
そして菌が繁殖しやすい環境を作ってしまったことにあります。
黄色(おうしょく)ブドウ球菌
一般的な環境の中に存在する細菌です。
この菌は人間の皮膚や鼻の中、口の中などに常在菌として存在します。
指などに傷がある場合に、食品を素手で触った場合に食品が汚染されて食中毒を引き起こすとされています。
菌が増殖すると強い毒素を作り出すため、かなり思い食中毒症状となります。
数時間以内に症状が現れます。
主な症状は、激しい嘔吐、腹痛、下痢、発熱などがあります。
セレウス菌
こちらも一般的な環境の中に存在する細菌です。この菌は、土壌、水、動物の腸内、人間の腸内など様々なところに見つかることがあります。
セレウス菌は熱に強いので、主に熱い状態で加熱された食品の保存不良や十分な加熱不足によって引き起こされることが知られています。
セレウス菌の感染は、加熱された食品を冷やしたり、冷たい食品を温めたりする際に菌が急速に増殖することによって発生することがあります。
食中毒の症状は、一般的には下痢や腹痛、腹部の不快感などの胃腸の症状が現れます。
これらの症状は感染から数時間から1日後に現れることが多く、通常は軽度から中等度の症状となります。
サルモネラ菌
サルモネラ菌は様々な動物や環境中に存在しています。感染すると食中毒や腸炎を引き起こす可能性があります。
サルモネラ菌による感染は、汚染された食品や水の摂取、感染動物との接触などによって広がります。
サルモネラ菌は腸管内で増殖し、毒素を産生することに症状を引き起こします。
通常、症状が発現するまでに12時間~72時間かかります。
一般的な症状には、下痢、吐き気、嘔吐、腹痛、発熱などがあります。通常は軽度から中等度の症状です。
その他にも原因菌はありますが、特に注意できるものとして、これらがあげられます。
まとめ
食中毒をおこす原因となるご飯の保存方法は、
- すぐに冷まさず温かいまま放置
- 常温で保存
- 再加熱を十分に行わなかった
- 保存容器が密閉できない
- 長時間保存した
です。
ご飯で食中毒を起こす菌には
- 黄色ブドウ球菌・・・傷があるのに手を洗わずに調理など(数時間以内にかなり強い症状がでる)
- セレウス菌・・・温かい状態で放置or加熱不足など(1日後に軽度から中等度の症状)
- サルモネラ菌・・・食材自体が最初から汚染(半日~3日後に軽度から中等度の症状)
などがあります。
調理の前、食事の前にはよくよく手を洗い、炊いたご飯は正しく保存しましょう。
咳などが出る場合にはマスクをして、手に傷があるならビニール手袋をするなど。菌が食材に入らないように調理の際も気をつけましょう。
炊いたご飯が余ったらすぐにラップを使っておにぎりを作り、冷凍保存して数日中に食べきるのもおすすめですよ!
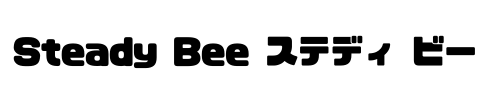


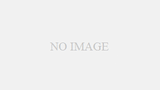
コメント