
暑くなると熱中症が怖いですね。
最近は「梅雨型熱中症」という言葉も聞きます。キーワードは「湿度」です。
この記事では、熱中症のなかでも梅雨時期 特有の「梅雨型熱中症」について簡単にお伝えします。
基本:熱中症とは
通常、36度から37度くらいに体温は保たれています。
ところが体内で作られた熱をうまく外に逃がすことができなくなると、体温がどんどん上がります。
暑い場所で長時間過ごしていたり、水分を取らなかったりするなど、「気温」「湿度」「熱(輻射熱)」が要因になって起こります。
体温があがることで体内の水分や塩分のバランスが崩れ、調節機能が働かなくなります。
そうなると体内の血液の流れが悪くなるので、汗もかけなくなり、熱放散や気化ができなくなります。
37度以下で臓器はうまく働くように作られています。そのため高熱になると脳を含む臓器が機能しにくくなります。
めまい、立ちくらみからはじまり、筋肉痛を起こしたりこむら返りが起こったりします。
頭痛、吐き気なども起き、だるさもでてきます。
ひどくなるとけいれんや失神、意識障害を起こすこともあります。
体の調子が悪くなるだけでなく、命に関わることもあるので、注意が必要です。
梅雨型熱中症
では梅雨型熱中症とはどのようなものでしょうか?
熱中症との違い
気温が低くても湿度が高いことが理由で熱中症になります。
気温が30度以下でも、湿度が85%あれば熱中症でいう「警戒」レベルです。
梅雨時期は湿度が高いので汗が蒸発できず、体の熱がさがりません。
通常は汗をかいても汗がひくときに体の熱をさげてくれるのですが、ずっとペタペタと皮膚の表面が湿っていて汗が蒸発せず体内が高温になります。
そのため気が付かないうちに熱中症になっています。
症状
疲労感、体の痛み、喉の乾き、汗が出ない、めまい、下痢、便秘、体が熱っぽい、尿が増える、頭痛、など
症状は多岐にわたります。風邪やコロナなどと勘違いするケースも。
予防法、対策
熱中症は「気温」「湿度」「輻射熱(輻射熱)」
その中で最も熱中症リスクが高いのが「湿度」です。
予防としては「湿度」を下げること。「除湿」です。
湿度の目安は50%。室温は28度。
湿度が高いと喉が乾きにくいので、いつの間にか脱水が進んでいることがあります。
喉がかわいていなくても、時間ごとに早め早めの水分補給をするように習慣づけないと危険です。
口の中がねばっとしたら脱水前のサインなので、こまめに飲みましょう。
また梅雨型熱中症の季節はまだ本格的な暑さに体が慣れていない状態なので、体を慣らしていくことが大切です。
お風呂に入ったり、短めの散歩や家事をしてうっすら汗をかくような作業をすると予防になります。
まとめ
本格的な暑さになる前の「梅雨型熱中症」
気温が低いからと安心していると、湿度の高さにやられてしまいます。
湿度は60%を超えたら除湿をして、体の表面がぺたぺたと湿っている状態を防ぎましょう。
みつばんはこまめにシャワーや汗ふきシートで体のペタペタをさらさらにしています。
外出時などはハンカチなどで首や顔の汗をこまめに拭くことで予防にもなりますよ。
街中ではなるべく日傘をさす、日陰を歩く、地下街を活用する、午前中や夕方に外出する、クールスポットを活用する など、日差しや熱に注意しながら過ごしましょう。
熱中症でつらい思いをすることがなくなりますように。
元気に暑さを乗り越えましょう!
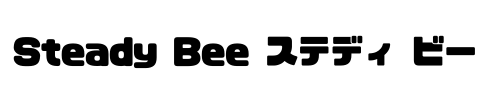



コメント